高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?
- いじめ

高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的ないじめ」が増加します。自立心が芽生える時期でもあるため、被害を抱え込みやすく、保護者が気付きにくいのも実情です。
もし、いじめのサインに気付いたときは、本人の自立心を尊重しながらも、状況に応じて積極的なサポートも検討しましょう。今回は、高校生に多い特徴的ないじめの形態や保護者が取るべき対応方法、相談先について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、高校生のいじめの特徴
文部科学省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」によると、高校生のいじめでは「仲間外れや無視」「パソコンや携帯電話などでの誹謗中傷」などの見えにくいいじめや、「冷やかしやからかい」「悪口や脅し文句」などの言葉を用いたいじめが多く報告されています。
以下では、高校生に多いいじめの傾向や特徴を説明します。
-
(1)仲間外れや無視など、認知されにくい心理的いじめが多い
「仲間外れ」「無視」といった心理的ないじめは、公立小学校でいじめ全体の12.2%となっており、中学校に進級すると8.9%に低下するものの、高校で再び13.8%と上昇します。
具体的には、クラスや部活動でグループに入れてもらえない、会話を意図的に避けられるなどの行為が挙げられるでしょう。
これらは、教師や保護者から見えにくく、被害者自身も「いじめと断定しにくい」ため、長期化・深刻化する可能性があります。外からは普通に学校生活を送っているように見えても、心の負担は大きく、孤立感や自己否定感を深めてしまうことが少なくありません。
参考:「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文部科学省) -
(2)SNSなどインターネットでのいじめの増加
こども家庭庁の令和6年度の統計によると、スマートフォンを使った高校生のインターネット利用率は97.6%で、多くの高校生の間でインターネット利用が日常となっていることが分かります。
SNSは広く普及しており、便利な半面、LINEグループからの排除、裏アカウントでの誹謗中傷、悪意ある写真や動画の拡散など、SNSやチャットツールを使ったいじめも深刻化しています。
ネットを介したSNSのいじめは、「24時間逃れられない」「一気に広がる」という特徴があり、精神的ダメージが大きくなるのが特徴です。
参考:「令和6年度 青少年のインターネット利用環境実態調査 調査結果」(こども家庭庁) -
(3)大学進学や就職など、進路への影響が大きい
高校でのいじめによる心身の不調や不登校は、進学や就職といった将来の進路選択に大きな影響を及ぼしかねません。保護者の方にとっても、子どもの学業や進路を心配する気持ちは自然なことです。
いじめのサインに気付いたときは、子どもの抱える不安に寄り添いながら、安心して次のステップに進めるようサポートしていく姿勢が大切です。
2、「もしかしていじめ?」高校生のいじめ被害のサインとは
高校生はいじめを受けていても「親に心配をかけたくない」「自分で解決したい」と考え、被害を隠してしまうことが少なくありません。
そのため保護者は、子どもの言葉だけでなく、行動や心身の変化からサインを感じ取ることが重要です。以下では、いじめの可能性を示す代表的なサインを紹介します。
-
(1)行動面に現れるサイン
行動の変化は比較的分かりやすいサインです。
行動面に現れるいじめのサインの例
- 登校に関する変化:遅刻や欠席が増える、保健室で過ごす時間が長くなる
- 持ち物の紛失や破損:理由を説明できない紛失や壊れた持ち物が目立つ
- スマホの扱いの変化:急に通知音を切る、画面を隠すなど、不自然にSNS利用を避ける
- 金銭の使い方の変化:説明のつかない出費や「小遣いが足りない」と頻繁にお金を欲しがる
こうした行動は、単なる思春期の反抗や嗜好の変化と区別がつきにくいこともありますが、継続的に見られる場合はいじめの兆候を疑う必要があります。
-
(2)情緒面に現れるサイン
心の変化は行動の変化に比べて分かりにくいですが、日常的な会話から察することが可能です。
情緒面に現れるいじめのサインの例
- 感情の起伏が極端になる:小さなことで涙ぐむ、怒りっぽくなる
- 自己評価の低下:「どうせ自分なんて」など自分を否定する発言が増える
- 将来への無関心:進路や夢の話を避ける、学習意欲を失う
- 過度の警戒心や緊張:スマホの通知に過敏に反応する、周囲を常に気にする
- 家族との交流を避ける:部屋に閉じこもる時間が増える、会話を避ける
このような兆候がみられる場合、いじめにより精神的なストレスを抱えている可能性を示しています。
-
(3)身体面に現れるサイン
いじめの影響は、体の不調として表れることもあります。
身体面に現れるいじめのサインの例
- 原因不明の体調不良:頭痛や腹痛、吐き気など医学的に原因が特定できない症状
- 睡眠の変化:不眠、悪夢、過眠
- 食習慣の変化:食欲が極端に減る、または過食傾向が見られる
- 自傷行為の痕跡:腕などに傷がある
- 容姿への過度の変化:突然外見に無関心になる、または過度に気にする
これらの症状が続く場合、心身が限界に達している可能性があるため、早急な対応が求められます。
3、高校生のいじめに対して保護者ができること
高校生のいじめに対して保護者が一方的に介入すると、子どもの自立心からかえって反発を招くことがあります。
そのため、本人の心情を尊重しつつ、必要なときに積極的に支援をするというバランスが重要です。以下では、高校生のいじめに対して保護者が取れる具体的な対応を説明します。
-
(1)本人の意向を尊重したヒアリングとメンタルケア
いじめ被害に遭った子どもは、いじめに遭っている事実を隠してしまうことがあります。保護者が聞き取りを行う際は、問い詰めるのではなく、安心して気持ちを話せる雰囲気づくりを心がけましょう。
会話では否定せずに傾聴を重視し、「どんなときも味方でいる」と伝えることが重要です。
さらに、必要に応じてスクールカウンセラーや心療内科など外部の専門家とつなぐことも検討してください。保護者だけで抱え込まず、周囲のサポートを受けることで子どもが少しずつ心を開きやすくなります。 -
(2)証拠収集
ネットいじめは、投稿やメッセージがすぐに削除されたり、加害者側が証拠を隠そうとしたりするケースが少なくありません。そのため、被害を後から証明できるように日頃から記録を残しておくことが大切です。
SNSやLINEの画面は、スクリーンショットを取り、保存日や状況をメモに書き添えることが有効です。学校や教育委員会、弁護士などに相談する際も、客観的な証拠があることで迅速かつ適切な対応が期待できるようになります。
特に、いじめに対する法的対応を検討する場合、証拠の有無が解決の方向性を大きく左右します。 -
(3)学校との適切な連携
いじめ問題を解決するためには、学校とのスムーズな連携が望ましいです。まずは担任や学年主任、生徒指導担当に状況を伝えるようにしましょう。その際は、事実を整理して冷静に話し、感情的にならないことが大切です。
また、面談内容や学校側の回答は記録に残しておくと、後々の対応に役立ちます。
学校が十分に対応してくれない場合は、教育委員会や第三者委員会への相談も視野に入れるべきです。保護者が一人で抱え込むのではなく、公的な制度や組織を活用することで、より客観的で効果的な対応が可能になります。 -
(4)外部の専門家との連携│スクールカウンセラー・弁護士等
学校内の対応には限界があるため、外部の専門家と連携することも大切です。
スクールカウンセラーは、子どもが抱える不安やストレスを軽減する役割を担います。また、弁護士は、加害者やその保護者との交渉、損害賠償請求、学校との交渉における法的助言など、具体的な解決手段を提供できます。特に、ネットいじめや金銭の絡む事案では、法的な視点が不可欠です。
早期に弁護士に相談しておくことで証拠整理や対応方針を確立でき、問題の長期化や被害の拡大を防ぐことにつながります。 -
(5)通信制、フリースクールへの転校など多様な進学ルートの検討
いじめにより学校生活を続けることが難しい場合、無理に在籍校に通い続けることが必ずしも正しい選択とは限りません。通信制高校やフリースクール、オンライン学習など、現在は多様な学びの場が整っています。新しい環境に移ることで、心の回復と学業の両立を目指すことも選択肢の一つです。
保護者は、「学校に通えなくても将来の道は開かれている」という希望を子どもに伝え、安心感を与えることが重要です。本人に合った学びの場を検討することで、子ども自身が再び前向きに進路を考えられるようになる場合もあります。
4、【段階別】高校生のいじめの相談先
高校生のいじめに直面したとき、どこに相談すればよいか迷う保護者も少なくありません。状況の深刻さに応じて相談先を選ぶことが大切であり、初期段階・深刻化・緊急時のそれぞれで取るべき行動は異なります。以下では、段階別に利用できる相談先とその役割を説明します。
-
(1)【初期段階】学校、スクールカウンセラー、地域の支援センター
重大事故など心身の被害が明らかでない場合、まずは、学校内外の身近な相談窓口を活用することをおすすめします。
学校は、子どもの生活の中心であり、担任や生徒指導担当が様子を見守っているのが通常です。また、学校と提携しているスクールカウンセラーに相談することで、心理的な不安の軽減や今後の対応方針の整理が期待できます。
さらに地域の子ども・家庭支援センターや教育相談窓口も心強い存在です。保護者が一人で抱え込まず、早期に複数の支援機関とつながることで、いじめの深刻化を防ぎやすくなります。
なお、弁護士は、初期段階からアドバイスのみの後方支援やサポートをすることも可能です。学校でのいじめ被害が深刻化する前に弁護士に相談することも有効です。 -
(2)【悪化・深刻化】教育委員会、弁護士
学校がいじめ調査を拒否する・回答に透明性がないなど対応が不十分な場合、また、いじめが長期化して子どもに影響がある場合には、教育委員会や弁護士へ早めに相談することをおすすめします。
教育委員会は、公立学校を監督する立場にあり、学校だけでは解決できない状況に介入する役割を果たします。
なお私立学校の場合、監督権限は都道府県知事にあります。各都道府県の私立学校事務主管課(自治体によって名称は異なる)が窓口となっており、相談や申し立てによって、当該高校に対する指導・助言・報告徴収などの対応が期待できます。
ただし、話し合いが進まない、子どもへの影響が深刻といった場合には、弁護士の関与が有効です。弁護士は法的視点から具体的な解決策を提示します。加害者側との交渉、損害賠償請求、学校対応に関する助言など、幅広いサポートが可能です。法的対応が必要な状況では、保護者だけで対応するのは困難ですので、なるべく早く弁護士にご相談ください。 -
(3)【緊急】弁護士、警察、医師
生命や安全に直結する深刻ないじめが確認された場合は、ためらわずに緊急対応を取ることが大切です。
暴力や恐喝など重大な行為があれば、まず警察に通報して子どもの安全を確保しましょう。また、心身の不調が見られる場合は、速やかに医師の診断・治療を受けさせることが重要です。同時に弁護士に相談することで、被害届の提出や加害者との交渉などを法的に支援してもらえます。
緊急時は、家庭だけで対応するのではなく、警察・医療・法律の三方向から迅速にサポートを受けることが、子どもの命と生活を守ることにつながります。参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
5、まとめ
高校生のいじめは、無視や仲間外れなどの心理的ないじめやSNSを通じたネットいじめなど、周囲からは見えにくいのが特徴です。保護者としては、子どもの小さな行動や感情の変化に気付き、早期に対応することが重要です。
ベリーベスト法律事務所の学校問題専門チームは、いじめ被害の解決に向けて、真摯にサポートを行います。また、学校や加害者との代理交渉はもちろん、穏便に解決を目指すためのアドバイスなども可能です。まずはお気軽にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
米澤 弘文
所属:東京弁護士会 登録番号:53503
学校問題専門チームのリーダーとして、いじめや退学、事故など、学校・保育園・幼稚園等の管理下で発生する問題に幅広く対応。
東京弁護士会「子どもの人権110番」では長年にわたり相談業務に従事しているほか、ラジオやWEBメディアを通じて学校トラブルに関する情報発信にも力を注ぐ。
- ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
いじめのコラム
-
更新日:2025年12月16日 公開日:2025年12月16日
- いじめ
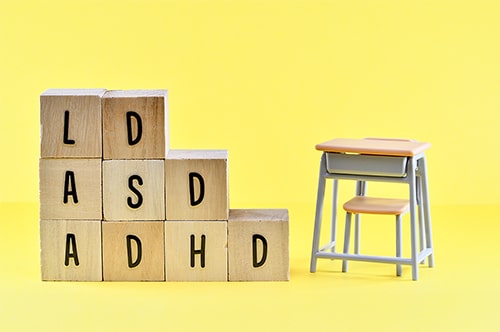 発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら
発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら -
更新日:2025年09月25日 公開日:2025年09月25日
- いじめ
 いじめによるPTSD|加害者への責任追及と保護者ができることいじめを受けた子どもが、その後、強い不安や恐怖に苦しみ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症するケースがあります。フラッシュバックや不眠、登校拒否といった…コラム全文はこちら
いじめによるPTSD|加害者への責任追及と保護者ができることいじめを受けた子どもが、その後、強い不安や恐怖に苦しみ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症するケースがあります。フラッシュバックや不眠、登校拒否といった…コラム全文はこちら -
更新日:2025年09月18日 公開日:2025年09月18日
- いじめ
 小学校で深刻化する「いじめ」被害児童の保護者が知るべき対策は?小学校におけるいじめ問題は、年々深刻さを増しています。特に小学2年生で11万6234件、3年生で11万1205件と、低学年での発生が突出しています。今回は、小…コラム全文はこちら
小学校で深刻化する「いじめ」被害児童の保護者が知るべき対策は?小学校におけるいじめ問題は、年々深刻さを増しています。特に小学2年生で11万6234件、3年生で11万1205件と、低学年での発生が突出しています。今回は、小…コラム全文はこちら
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
通話