いじめによるPTSD|加害者への責任追及と保護者ができること
- いじめ

いじめを受けた子どもが、その後、強い不安や恐怖に苦しみ、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症するケースがあります。フラッシュバックや不眠、登校拒否といった症状が主なため、保護者がそうしたサインにいち早く気付くことが大切です。
また、PTSDと医師に診断された場合、「後遺障害等級は認定されるのか」「学校や加害者へ責任追及できるのか」と悩む方もいるでしょう。
今回は、いじめによるPTSDの特徴やサイン、後遺障害認定や損害賠償請求の可能性などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、いじめにおけるPTSD
いじめによる不安や恐怖、苦しみを抱える子どもの中には、トラウマ(心理的外傷)からPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症するケースもあります。
保護者は、早期に子どもの異変に気付き、適切な対応をとることが重要です。
-
(1)子どもに異変? トラウマ反応に気付く
いじめを受けた子どもは、心の中で強い恐怖や恥、無力感といった感情を抱えます。
それにより、以下のようなトラウマ反応が表れることがあります。
トラウマ反応│具体的なケース 情緒 - 恐怖・怒り・抑うつ
- 分離不安・退行(赤ちゃん返り)
- フラッシュバック
- 感情の麻ひ
- 睡眠障害
行動 - 落ち着きがない
- イライラしている
- 集中力の低下
- 衝動的(暴力・自傷)
- 非行・薬物乱用
身体 - 吐き気・おう吐
- 頭痛・腹痛などの身体の痛み
- かゆみなどの皮膚症状
認知 - 安全感や信頼感の喪失
- 罪悪感
- 自尊感情の低下
- さまざまな対人トラブル
参考:「学校における子供の心のケア-サインを見逃さないために- P.33」(文部科学省)
こうしたトラウマ反応の一環として、学習面において次のような行動が現れることがあります。- 登校拒否
- 成績が低下する
- 宿題や持ち物を忘れることが頻発
なお、トラウマとは強い精神的ショック(心理的外傷)であり、医学的診断名ではありません。心理学・精神医学などの領域で使用される言葉です。
トラウマ体験によるさまざまな反応は自然治癒するケースも少なくありませんが、放置することで長期化・悪化しPTSDとして精神疾患に発展する恐れもあります。 -
(2)PTSDの症状│特徴やサイン
PTSDとは、強いストレス体験をきっかけに心の働きに障害が表れる精神疾患です。医学的な基準に従って診断されます。
PTSDの主な症状には、以下のようなものがあります。
外傷となった出来事の侵入(フラッシュバック) 特に意識していない状況下でも、いじめの場面を急に思い出す、夢に出てくる、教室や校舎に入ると、極度の恐怖や不安に襲われるなど、いじめがあたかも繰り返されるような解離的症状(フラッシュバック症状)が生じる。 外傷体験に対する持続的な回避 いじめやこれに関連した不快な記憶を考え、感情を回避したり、いじめを思い出させるような場所や人物などを回避したりすること。たとえば「学校に行きたがらない」「いじめがあった教室に入れない」などが典型。 外傷体験に関連する認知や感情のネガティブな変化 いじめとなった出来事の重要な局面を思い出せない、自分あるいは他者に対しての信頼や期待が全く持てない、いじめの原因や結果に対して自分や他者の非難につながるような曲解した思考しかできないなどの状態。また、興味や社会参加の極端な減退、他者に対する疎外感が生じる。 外傷となった出来事に関連する覚醒度や反応性の変化 イライラした態度や激しい怒り、自己破壊的な行動、過覚醒、集中困難、睡眠障害など。 これらの症状が1か月以上持続し、日常生活に支障をきたしている場合は、PTSDが疑われます。また、いじめの体験後、数週から数か月に及ぶ潜伏期間を経て発症することもあります。
いじめによる精神的ダメージは時間の経過とともに消えるとは限らず、むしろ悪化する場合もあるため、早期の治療が求められます。 -
(3)【事例】いじめが原因でPTSDになり不登校となったケース
中部地方の小学校で発生したいじめ被害が、「重大事態」として自治体の第三者委員会で調査され、その報告書が取りまとめられました。
報告書によると、男子児童は複数の同級生から- 殴る、蹴るなどの暴行
- 川に引き込まれる
といった身体的ないじめを繰り返し受け、心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症した結果、不登校となりました。
児童の母親は「子どもの症状を信じてもらえず、学校との交渉も非常に困難だった」と述べており、学校や教育委員会による支援体制の不備が報告書でも指摘されています。
なおこの事案では、教育委員会が第三者委員会の報告書を公表せず、保護者や代理人弁護士にも報告書の写しを渡さず、手書きで書き写すよう求めたことも問題視されています。
2、弁護士へ相談を検討すべきケースとは?
以下のようなケースに該当する場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)いじめによるPTSD(精神的・身体的な被害)がある
PTSDは一過性の心の不調ではなく、病院での治療を要する精神障害にあたります。フラッシュバック、不眠、不登校などが長期に及ぶことで、学業・人間関係・将来の進路選択などに深刻な影響を及ぼす恐れがあります。
保護者の方は、子どもに寄り添って回復を見守ることが喫緊の課題となるでしょう。学校や加害者側とのやりとり、法的責任の追及は早期に弁護士に任せ、心の傷を回復させるために治療に専念することをおすすめします。 -
(2)加害者側から謝罪や対応がない
いじめ加害者やその保護者が謝罪や補償の意思を示さず、事実関係を否定している場合、被害者側の精神的な負担は大きなものとなるでしょう。
そのようなときは弁護士が介入し、被害者の代わりとなって誠実な謝罪の要求や交渉を行うことも考えられます。いじめ問題の解決は長い時間を要することも珍しくありません。信頼できる弁護士のサポートを受けながら一歩ずつ進めていきましょう。 -
(3)学校側がいじめを認めない
学校や教育委員会が「いじめの存在はない」「当事者間で解決した」などとして、いじめの認定を拒否したり、問題を矮小化したりするケースがあります。
文部科学省の「いじめ防止対策推進法」では、子どもに重大な被害が生じた場合には「重大事態」として調査を行うことが義務付けられています。PTSDが発症する程のいじめであれば、重大事態である可能性を軽視できるものではありません。
しかし実際には、学校や教育委員会が不誠実な対応をとるケースも散見されます。
弁護士は、証拠収集のサポートや学校や教育委員会とのやりとりを代理で行い、法的知識に基づいて、いじめの実態を明らかにすることを求めます。
3、いじめのPTSDは後遺障害等級認定される?
いじめが原因でうつ病やPTSDを発症し、長期間にわたって通学や日常生活に支障がある場合、公的な支援や補償の対象となることがあります。
ここでは、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる「災害共済給付制度」による後遺障害等級認定について説明します。
-
(1)まずは日本スポーツ振興センターに等級認定の申請をする
学校管理下におけるいじめによりPTSDなどの傷病が生じた場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」を利用して医療費や後遺障害見舞金の申請ができる可能性があります。
この制度は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入している小中高校などに在籍する児童・生徒が、授業や部活動、登下校中などに災害(けが・病気)に遭った場合、一定の給付を受けられるものです。
いじめによる疾病も含まれていますので、医師の診断によりPTSDとされた場合、後遺障害等級認定が受けられる可能性があります。 -
(2)後遺障害等級が認められない、不当な場合は異議申し立てが可能
PTSDのような精神障害は、身体的後遺障害と異なり、外見から判断しにくいため、等級認定を巡って判断が分かれる場合があります。
医師の意見書や診断書、通院記録、カウンセリングの内容など十分な資料を提出しても「後遺障害とは認められない」とされるケースも存在します。
そのような場合は、日本スポーツ振興センターに対して異議申し立て(不服審査請求)を行うことが可能です。申請に不備があった場合や、症状の深刻さが十分に説明されていない場合には、不備の是正や追加資料を提出することで認定が覆る可能性もあります。 -
(3)適切な後遺障害等級認定は、弁護士のサポートが重要
PTSDなどの精神的後遺障害の認定には、法律・医療両面の専門知識が必要になります。書類の整備、証拠資料の精査、主張の根拠付けなどは、弁護士のサポートを受けることでスムーズに進めることが可能となるでしょう。
弁護士は、以下のようなサポートを行います。- 医師の診断書や通院記録の法的活用方法のアドバイス
- 認定が不当な場合の異議申し立ての代理
- 給付金とは別に加害者への損害賠償請求手続きも併行して対応
こうした制度の活用には期限があるため、迷ったら早めに弁護士へ相談することが、子どもの回復と将来を守る第一歩となります。
4、いじめによるPTSDで弁護士ができること
「いじめ」と「PTSD」の因果関係を立証することは難しく、問題の矮小化や隠蔽(いんぺい)が行われるリスクがあります。
いじめを受けた子どもがPTSDを発症した場合、弁護士のサポートを適切に受けることが重要です。いじめによるPTSDに対して、弁護士は以下のサポートを行います。
-
(1)いじめの証拠収集のサポート
いじめとPTSDとの因果関係を示すには、被害の経緯や実態を証明する証拠が必要です。たとえば、以下のようなものが、証拠として役立ちます。
- 子どものメモやLINEのやりとり
- 担任や学校とのやりとり記録
- 診断書、通院履歴、カウンセラーの意見
- 学校でのアンケートや報告書(第三者委員会報告書など)
弁護士は、こうした証拠の収集方法をアドバイスするとともに、必要に応じて情報開示請求など法的手段を用いた調査も行うことができます。
-
(2)学校、教育委員会、加害者親との代理交渉
被害の補償や再発防止策を求める際に、学校や教育委員会、加害児童生徒の保護者と直接交渉を行うのは、保護者にとって大きな精神的負担になります。特に、学校側が責任回避的な態度を取ったり、加害者側が話し合いを拒否したりするケースでは、保護者のみでは対応が難しく、感情的な対立に発展する恐れもあります。
このような場合、弁護士が代理人として対応すれば、法的根拠に基づく冷静な交渉が可能となり、保護者が過剰なストレスを抱えることなく問題解決を目指せるでしょう。 -
(3)損害賠償請求や刑事告訴の判断、法的手続き
加害者に対して損害賠償請求や慰謝料請求を行うには、いじめ行為によって被害が生じたことを法的に立証する必要があります。また、場合によっては暴行・傷害などの刑事告訴も検討する必要があります。
弁護士は、被害の内容と法的責任を精査し、どのような法的手続きが適切かを判断し、必要な準備と実行を担います。損害賠償請求や刑事告訴の手続きもすべて弁護士に任せることができます。 -
(4)いじめの損害賠償請求の時効に留意して手続きできる
いじめによる損害賠償請求には、時効があります。加害者に対して損害賠償請求をするなら時効期間に注意して進めていかなければなりません。
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、損害および加害者を知ったときから3年で時効になりますが、いじめによりPTSDを発症した場合、それが生命・身体を害するものであると評価されれば時効期間が5年に延長されます。
3年または5年のいずれの時効期間が適用されるかは、具体的な事案によって異なりますので、判断に迷うときは早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。 -
(5)二次被害の防止支援
いじめ問題が公になると、被害者や保護者が「告発者」として周囲から誤解を受けたり、学校内でさらなる孤立や偏見にさらされたりするといった「二次被害」が生じることがあります。
いじめ問題に携わる弁護士は、このような二次被害が起こらないよう、防止支援を行いながら手続きを進めるよう尽力します。子どもが安心して生活できる環境を整備するためにも、弁護士と協力し、アドバイスを受けながら対応していくことをおすすめします。参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
5、まとめ
いじめとPTSDの因果関係の立証は、発生してから時間が経過していたり、学校側が矮小化や隠蔽したりして、困難なケースも少なくありません。
そのため、事実の整理や証拠の保全には弁護士の支援が重要です。特に、損害賠償請求や刑事告訴など法的な対応を検討する場合は、法律の知識と実務経験をもつ弁護士のサポートを求めることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、学校事故やいじめ解決に精通した「学校問題専門チーム」があり、保護者や児童・生徒の立場に寄り添った対応を行っています。
いじめによるPTSDでお悩みの方は、どうかお一人で抱え込まず、当事務所までご相談ください。

ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
米澤 弘文
所属:東京弁護士会 登録番号:53503
学校問題専門チームのリーダーとして、いじめや退学、事故など、学校・保育園・幼稚園等の管理下で発生する問題に幅広く対応。
東京弁護士会「子どもの人権110番」では長年にわたり相談業務に従事しているほか、ラジオやWEBメディアを通じて学校トラブルに関する情報発信にも力を注ぐ。
- ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
いじめのコラム
-
更新日:2026年02月02日 公開日:2026年02月02日
- いじめ
 性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら
性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら -
更新日:2025年12月16日 公開日:2025年12月16日
- いじめ
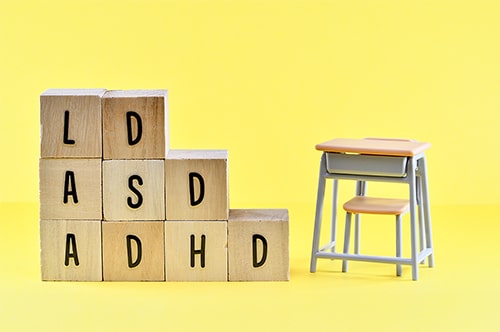 発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら
発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら -
更新日:2025年10月22日 公開日:2025年10月22日
- いじめ
 高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
通話