小学校で深刻化する「いじめ」被害児童の保護者が知るべき対策は?
- いじめ

小学校におけるいじめ問題は、年々深刻さを増しています。特に小学2年生で11万6234件、3年生で11万1205件と、低学年での発生が突出しています。
今回は、小学校でのいじめが「重大事態」として扱われた事例や訴訟で損害賠償が認められたケースをもとに、いじめの際に保護者がとるべき具体的な対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
参考:「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」(文部科学省)
1、増え続ける小学校のいじめ
文部科学省調査によると、令和5年度のいじめ認知件数は過去最多を更新しました。また、小学2年生がもっともいじめが多い学年で、いじめの低年齢化が進んでいます。
以下では、実際の統計資料をもとに小学校でのいじめの現状を説明します。
-
(1)いじめのピークは「小2」
近年、小学校におけるいじめの認知件数は著しく増加しています。文部科学省の統計によると、いじめの認知件数は全国で73万件を超え、過去最多を更新しました。
特に、小学校のいじめの中でも認知件数がもっとも多いのが「2年生」、次いで「3年生」「1年生」と、低学年であることも明らかになっています。
小学校の学年別いじめの認知件数1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 令和3年度 9万6142件 10万976件 9万4781件 8万4125件 7万1991件 5万3016件 令和4年度 10万4111件 11万42件 10万4532件 9万3749件 7万9720件 6万357件 令和5年度 10万7936件 11万6234件 11万1205件 10万1097件 8万6102件 6万7028件 -
(2)「いじり」「からかい」どこからいじめ?
小学校では、「いじり」や「からかい」は日常的なコミュニケーションと捉えている児童もいるかもしれません。しかし、受け手が「つらい」「やめてほしい」と感じた時点で、それはいじめと定義されるでしょう。
具体的には、以下の行為がいじめとして挙げられます。- 冷やかし、からかい、悪口などを言われる
- 遊ぶふりをしながら、たたく、蹴るなどの暴力行為をされる
- 無視や仲間外れをされる
- 恥ずかしいこと、嫌なことを無理やりさせられる
-
(3)知っておきたい「いじめの重大事態」とは
「いじめの重大事態」とは、いじめによって児童が生命や身体、心身の健康、財産などに深刻な被害を受けた、または長期間学校に通えなくなるなどの著しい影響があったと認められる場合をいいます。
これらのいずれかに該当する事態が発生したとき、学校は速やかに教育委員会・行政機関などに報告し、調査委員会などによる客観的な調査を実施する義務があります。
いじめの重大事態は、いじめ防止対策推進法第28条第1項に基づいて定義されており、以下の2つに分類されます。
類型 内容 第1号 いじめによって児童等の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合 第2号 いじめにより児童等が相当の期間(通常30日以上)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合 以下は、文部科学省が公表した令和5年度の「いじめの重大事態」の件数(学校種別)です。
小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 合計 重大事態発生校数 506 444 227 8 1185 重大事態発生件数 548 491 259 8 1306 うち第1号 238 245 162 3 648 生命 17 43 15 0 75 身体 49 44 24 0 117 精神 153 134 117 2 406 金品等 19 24 6 1 50 うち第2号 391 320 148 5 864
これによると令和5年度の重大事態件数は、1306件と、過去最多を更新しています。特に、小学校での発生件数が548件ともっとも多く、学校種別の合計では、直近10年間で最多の発生件数となっています。
2、【裁判例・事例】小学校のいじめ
いじめは、場合によっては不登校やPTSD(心的外傷後ストレス障害)を引き起こし、重大な精神的・身体的被害をもたらします。
以下では、小学校におけるいじめについての実際の裁判例や事例を紹介します。
-
(1)いじめによる不登校│「学習権の侵害」が認められた裁判例
- 民事裁判を起こした側(原告):いじめ被害で不登校になった元児童とその保護者
- 訴えられた側(被告)
① 元被害児童の通っていた小学校を設置している市
② いじめ加害者とされた元児童2名
大阪府の小学校で、男子児童がいじめにより不登校に陥った事件では、いじめ被害を受けた原告が市と加害児童らを相手取り、計680万円の損害賠償を求めた訴訟が提起されました。
原告の男子児童は、同級生からの仲間外れや「受験勉強で休んでいる」などの事実無根のうわさにより不登校となり、学校生活から長期間離脱しました。その後、市の教育委員会は、いじめ防止対策推進法上の「重大事態」と認定し、学校はクラス全体にアンケートを実施し、同級生3人が発言者として浮上しました。しかし、児童の母親が誰の発言かを問い合わせた際、校長は情報を提供しませんでした。
この対応について、大阪地裁(第一審)は「学校の裁量を逸脱した違法な対応」と認定。もし適切に対応していれば、男子児童が教室に復帰できた可能性があるとして、「学習権が侵害された」と明示しました。一審判決は、学習権侵害による慰謝料として、市に50万円の支払いを命じました。
控訴審(第二審)の大阪高裁もこの判断を支持。さらに両親への対応についても損害賠償責任を認め、両親それぞれに慰謝料として5万円の支払いを加えた計60万円の支払いを市に命じました。【ポイント】
- 不登校が長期化し、教室に復帰できなかったことで「学習権侵害」が明示された画期的判決
- 重大事態認定後の学校対応において、事前説明や情報提供を怠ったことが違法と判断
- 文部科学省ガイドラインやいじめ防止対策推進法の基準が、学校の法的責任の判断基準となった
-
(2)私立小での「重大事態」│心身被害に損害賠償が認められた裁判例
- 民事裁判を起こした側(原告):他の児童の行為によりケガをし、退学・転校した元児童とその保護者
- 訴えられた側(被告):元児童の通っていた小学校を運営する学校法人
静岡県の私立小学校で発生した事案です。この事案では、男子児童が班別活動中、年下の女子児童の足が顔面に直撃し、前歯が折れる重傷を負い、のちに退学・転校しました。男子児童と両親は「重大事態」に該当するにもかかわらず、学校法人が適切な調査を行わなかったとして損害賠償請求訴訟を提起しました。
令和7年1月、静岡地裁は、「児童はいじめにより身体への重大な被害を受け、心身に重大な影響が出た疑いがある。本件は重大事態に該当し、学校側は法的義務として調査を行うべきであった」と述べ、学校法人に55万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
このように、被害の程度が一定以上に及んだ場合は、加害児童の意図や継続性にかかわらず、調査を怠ったこと自体が違法と評価されうることが裁判所により明示されました。【ポイント】
- 歯を折るなどの身体的被害は、「重大事態」の典型的ケースとされる
- 加害児童が年下であっても、被害の重大性をもって重大事態と判断される
- 私立校であっても、調査義務を怠れば学校法人に損害賠償責任が発生
-
(3)いじめによるPTSD│教育委員会が重大事態を認定した事例
- 民事裁判を起こした側(原告):いじめ被害で不登校になり、PTSDの診断を受けた元児童とその保護者
- 訴えられた側(被告):元被害児童の通っていた小学校の設置者である地方自治体
三重県の小学校では、当時小学2年生だった男子児童が同級生からのいじめ被害によりPTSD(心的外傷後ストレス障害)と診断される深刻な事態が発生しました。
児童は、消しゴムをゴミ箱に捨てられる、女子トイレに押し込まれるなどのいじめを複数の同級生から受けていました。児童が「学校に行きたくない」と母親に訴え、担任教員は加害児童に謝罪をさせる対応をとったものの、翌年以降もいじめは継続。男子児童はPTSDと診断され、不登校状態となりました。
この深刻な経過を受けて、町の教育委員会は、「いじめの重大事態」に該当すると認定。設置された第三者委員会は、報告書で、学校の対応について「表面的な行為の指導にとどまり、組織的な対応が不十分だった」として厳しく指摘しました。
現在、被害児童側は「いじめ防止法に基づく適切な対応がとられなかった」として、町と県を相手取って損害賠償を求める訴訟を提起しており、係争中です。【ポイント】
- 精神的後遺症であるPTSDも「心身への重大な被害」に該当し、重大事態と認定されうる
- 担任レベルでの対応にとどまり、学校全体での対応がなされなかった点が問題視された
- 重大事態の認定がなされた場合、教育委員会・学校には調査義務が発生し、それを怠ると訴訟に発展する可能性がある
3、いじめトラブルで保護者がすべきことは?
小学生、特に低学年の子どもは、いじめの被害を受けても「何が起きたのか」「どう感じているのか」をうまく言葉にできないことがあります。
そのため、保護者は子どもの小さな変化を見逃さず、段階的・計画的に対応することが重要です。
-
(1)【初期対応】子どもの話を丁寧に聞く
まずは、子どもの気持ちに寄り添いながら、安心して話せる環境を整えることが大切です。問い詰めるような口調ではなく、「何か困っていることはない?」「最近学校どう?」といった日常的な対話の中で変化に気づく姿勢をもちましょう。
子どもは、「親に知られたくない」という気持ちから、いじめにあっていても話せないケースも多いため、すぐに聞き出そうとするのではなく、時間をかけてじっくりと話を聞いてあげてください。 -
(2)【記録】状況をメモ・保存しておく
いじめの内容を把握したら、できるだけ早い段階でメモをとったり証拠を残したりするようにしましょう。記録しておくべき内容は、以下のとおりです。
- 被害があった日時、場所、内容
- 加害児童の名前
- 子どもの言動や体調の変化
- 学校とのやり取りの内容や日時
いじめによる暴力でケガをした場合には、必ず病院で診察を受け、診断書を取得しておきましょう。後に損害賠償や重大事態認定を求める場合に、重要な証拠となります。
-
(3)【相談1】担任・校長・スクールカウンセラーに連絡
最初の対応は、担任教員に報告するのが基本ですが、現場の教員以外の視点も大切です。校長やスクールカウンセラーへの相談も検討しましょう。
相談時のポイントは、「何が起きたか」「どのような対応を希望するか」を明確に伝えることです。その際には、感情的にならないよう冷静に話をするように心がけましょう。
学校側とのやり取りは、メールや連絡帳など記録が残る方法で行うと、後々のトラブル防止に役立ちます。
また、この時点で学校問題の弁護士に相談することも有効です。証拠収集や交渉の仕方のアドバイス、代理交渉など状況に応じたサポートを求めましょう。 -
(4)【相談2】国・都道府県等の相談窓口
学校での対応が不十分と感じた場合には、外部の相談窓口を活用することも選択肢の一つです。
- 各都道府県の「いじめ問題相談窓口」
- 文部科学省「24時間子供SOSダイヤル」
- 法務局の「子どもの人権110番」
これらの窓口は、保護者や子どもからの匿名相談も受け付けています。
-
(5)【相談3】弁護士
いじめによる心身の被害が大きい場合や、学校が対応に消極的な場合には、弁護士への相談を検討すべきです。
弁護士は、- 学校や教育委員会と交渉する際の助言
- 損害賠償請求の可否判断
- 調査資料の開示請求や重大事態認定への支援
など、法的な観点から被害児童と家族をサポートします。
特に、学校や加害者側に責任追及したい、法的な措置も検討したい、といった場合は早めに弁護士に相談することをおすすめします。
4、いつ相談? 弁護士依頼の境界線
いじめが発覚しても「弁護士に相談してもいいのだろうか?」と悩む保護者の方も少なくありません。以下では、いじめ問題を弁護士に相談すべきタイミングの目安を4つの観点から説明します。
-
(1)心や身体に重大な影響が出ている
以下のケースのように、心身の健康に深刻な影響が出ている場合、すでに「重大事態」に該当している可能性があります。
- 不登校が長期化している
- 食欲不振や睡眠障害など体調面に変化がある
- 医師からPTSDや抑うつ状態と診断された
学校や教育委員会の調査対応が適切かどうか、弁護士の目でチェックしてもらうことが有効です。
-
(2)学校が「いじめ」を認めない
「本人がそう感じていない」「ふざけていただけ」「証拠がない」といった理由で、学校がいじめの事実を否定・回避するケースも少なくありません。
このような場合、保護者側が冷静かつ法的に根拠のある主張を行うためには、弁護士のサポートを受けることを検討しましょう。弁護士が介入することで重大事態の調査義務や証拠の開示請求も視野に入れた対応が可能になります。 -
(3)学校、保護者間のトラブルを避けたい
大切な我が子が被害に遭った場合、冷静さを保つのは難しいものです。
学校や加害児童の保護者との話し合いが感情的になりそうなときには、第三者として弁護士を介入させることで冷静な対応を目指しましょう。
また、学校に対しても、保護者からの要望としてではなく「法的要求」として伝えることにより、真剣な対応を引き出せる可能性があります。 -
(4)損害賠償請求を検討している
いじめによってお子さんが精神的・身体的な苦痛を受けた場合、学校や加害者に対して慰謝料などの損害賠償を請求できる場合があります。
たとえば、以下のような状況があれば、弁護士に相談すべき段階です。- 学校が調査を怠った(重大事態の調査義務違反)
- 教育委員会の対応が不十分
- 加害児童の行為が悪質・継続的である
- 医師の診断書など客観的証拠がある
弁護士は、証拠の整理から、請求金額の算定、学校や自治体との交渉まで一連の対応が可能です。保護者の負担を軽減しながら、法的責任追及の実現を目指します。
参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
5、まとめ
小学校でのいじめは年々低年齢化が進んでいます。低学年の子どもは状況をうまく伝えられず、保護者も対応に迷う場面が多いのが現実です。しかし、見過ごせば心身に深い傷を残し、将来的な影響にまで及ぶ可能性があります。
いじめは家庭だけで抱え込むべき問題ではありません。ケースに応じて、学校、行政、そして弁護士との連携をとり、事態の改善を目指しましょう。小学校のいじめ問題は、学校問題専門チームがあるベリーベスト法律事務所までご相談ください。

ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
米澤 弘文
所属:東京弁護士会 登録番号:53503
学校問題専門チームのリーダーとして、いじめや退学、事故など、学校・保育園・幼稚園等の管理下で発生する問題に幅広く対応。
東京弁護士会「子どもの人権110番」では長年にわたり相談業務に従事しているほか、ラジオやWEBメディアを通じて学校トラブルに関する情報発信にも力を注ぐ。
- ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
いじめのコラム
-
更新日:2026年02月02日 公開日:2026年02月02日
- いじめ
 性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら
性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら -
更新日:2025年12月16日 公開日:2025年12月16日
- いじめ
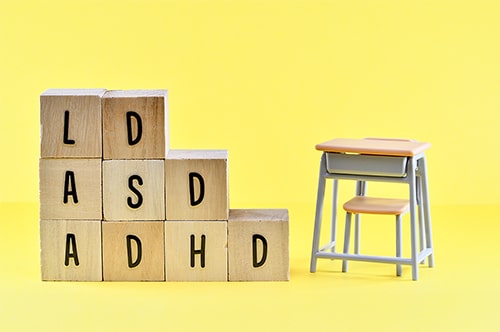 発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら
発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら -
更新日:2025年10月22日 公開日:2025年10月22日
- いじめ
 高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
通話