中学生のいじめ・具体的ケース│チェックリストで判断し、弁護士へ相談を
- いじめ
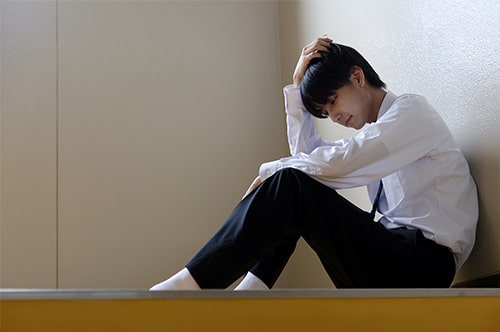
文部科学省の令和5年度の調査報告によると、中学校のいじめの認知件数は、3年連続で増加しています。
中学生になると友人や異性との関係が複雑化する一方、保護者とのコミュニケーションは希薄になり、いじめに気付きにくいケースも少なくありません。
本記事では、中学生のいじめの現状、子どもの様子に異変を感じた場合のチェックリスト、いじめから我が子を守るため対策等について弁護士が解説します。
1、中学生が直面しやすい「いじめ」の状況
文部科学省(文科省)が行った行政調査では、直近10年間の中学校でのいじめの認知件数は微増傾向であることが報告されています。
-
(1)中学校のいじめ認知件数は増加傾向
加速度的に進む子どもの人口減少にもかかわらず、中学校におけるいじめ認知件数は、平成25年(5万5248件)から増加し続けています。
参考:「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文部科学省)
新型コロナウイルスの影響により令和2年度に一時的に減少しましたが、その後は再び増加に転じ、令和5年度では前年比10.1%、10年前と比較すると2倍以上の12万2703件に達しました。
なお、いじめの認知件数の増加は、学校が積極的にいじめを認知し、早期対策に取り組んだという側面もあります。2章や3章でも後述しますが、いじめが疑われる場合は、冷静に状況を把握し、ベストな相談先を選ぶことが大切です。 -
(2)学年別いじめの認知件数|中1がもっとも多いのはなぜ?
文部科学省の公表している学年別のいじめの認知件数によると、中学生では、中学1年生でもっとも件数が多く、学年が進むに連れて減少する傾向にあります。
学年別いじめの認知件数中学1年生 中学2年生 中学3年生 令和3年度 5万1293件 3万2190件 1万5041件 令和4年度 5万8068件 3万5743件 1万8235件 令和5年度 6万3778件 3万9031件 2万508件 参考:「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文部科学省)
この理由は、中学1年生がもっとも人間関係の変化が大きい学年であることが一因と考えられます。新しい生活やクラスメートへの不安、心理的な負担が多い環境は、いじめが起こりやすいでしょう。
子どもの相互理解やコミュニケーションスキルは、学年が上がるにつれ向上し、中学3年生になると、いじめの認知は1年生の約3分の1に留まります。 -
(3)中学校でよく見られるいじめのパターン
中学校で多い、いじめのパターンは以下の通りです。
中学校のいじめの態様状況
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる(63.6%※)
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをしてたたかれたり、蹴られたりする(14.0%)
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする(9.4%)
- パソコンや携帯電話等で、ひぼう・中傷や嫌なことをされる。(9.2%)
- 仲間はずれ、集団による無視をされる(9.1%)
参考:「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」(文部科学省)
中学校でもっとも多い“言葉の攻撃”は、大人が気付くにくい、見えないいじめの典型といえます。
自分がいじめの対象となっていることを知られたくないという心理や、仮に伝えても教師や保護者からは「冗談では?」「気にする程ではない」と言われるかもしれないという恐れから、発覚が遅れて深刻化するケースもあります。
いじめを見逃さないためには、次章でご紹介するチェックリストなどで確認することをおすすめします。
2、【チェックリスト】いじめの判断ポイント
「からかい」や「ふざけながら蹴る・たたく」「無視」など、中学校でよくあるいじめの態様は、被害者がいじめかどうか判断に迷ったり、いじめではないと言い張ったりするケースがあります。
しかし、子どもが深刻な精神的ダメージを負っているのであれば、保護者としては、できる限り早い段階で対応することが大切です。
まずは子どもと話をする中で、以下の項目に当てはまらないか、確認してみましょう。
| いじめチェックリスト |
|---|
① 本人の精神状態は?
② 周囲の反応は?
③ 行為の状況は?
|
上記のリストはあくまで一例です。本人がつらい状態であれば、国や都道府県の相談窓口、弁護士などに相談し解決を図りましょう。
3、いじめから子どもを守るための方法・対応手順
いじめから子どもを守るためには、事実関係の把握や証拠の確保などを行ったうえで、学校側に適切な対応を求めましょう。弁護士のサポートを受けることも有力な手段です。
具体的には、以下の手順で対応しましょう。
-
(1)子どもからよく話を聞く
まずは子どもと話をして、いじめに関する事情をよく聞きましょう。前掲のチェックリストを活用し、何をされているのか、本人はどのように感じているのか、どういった解決を望むのかなどを丁寧に聞き取ることが大切です。
大人が介入することで、さまざまな解決方法があることを伝え、精神的な安定を取り戻せるよう、心に寄り添ってヒアリングを行いましょう。 -
(2)いじめに関する証拠を確保する
子どもがいじめを受けていることが分かった場合は、いじめに関する証拠をできる限り確保しましょう。いじめの証拠を十分に確保すれば、学校・加害者との交渉や損害賠償請求などに役立ちます。
たとえば、以下は有力な証拠になりえます。- いじめが起こった日付や内容を記したメモ、日記
- いじめを示すSNSのやりとりのスクリーンショット
- 体にできた傷やあざの写真
- ケガをした場合の診断書
- 学校とのやりとりの記録
可能であれば、いじめを目撃した第三者の証言や録音データなども集められれば、事実の裏付けとして活用できます。証拠は時系列で整理しておくと、学校や弁護士に相談する際にもスムーズです。
-
(3)学校へ連絡して対応を求める
子どもがいじめの被害を受けていることは、速やかに学校側へ共有し、連携して解決を目指すことが大切です。学校側の協力を得られれば、教員が子どもを守ったり、加害生徒に対して指導したりすることで、解決することがあります。
ただし、学校側がいじめを「単なる子ども同士のトラブル」と捉えて対応を後回しにしたり、事実関係の確認に消極的だったりするケースもあります。
そのような場合には、教育委員会などの第三者機関に相談する、弁護士を通じていじめの調査や情報開示を申し入れるなど、外部の力を借りて適切な対応を促すことが必要です。また、学校とのやりとりは記録を残しておくことで、万が一の法的対応にも備えやすくなります。 -
(4)弁護士へ相談する
学校側がいじめについて適切な対応をとらない場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。また、加害生徒や学校に対して損害賠償を請求する場合も、弁護士のサポートが役立ちます。
中学校でのいじめに関して弁護士ができることについては、次の項目で詳しく解説します。
4、中学校でのいじめについて弁護士ができること
中学校に通う子どもをいじめから救い出すためには、弁護士と連携して対応しましょう。弁護士は、中学校でのいじめ被害を解決するため、以下のようなサポートを行っています。
-
(1)いじめ被害の解決策のアドバイス
いじめ被害を解決するためには、状況に応じた適切なアプローチで対応する必要があります。その際には、法的な視点からのアドバイスも有効です。
弁護士は、有効ないじめの証拠の集め方や、学校や加害生徒側への対応方法を整理し、いじめ被害者の状況に寄り添ったアドバイスを行います。
「なるべく穏便に解決したい」「弁護士の介入を知られたくない」という場合は、弁護士から交渉方法のアドバイスを受け、保護者の方がご自身で学校側とやり取りをすることも可能です。 -
(2)再発防止に向けた学校側への働きかけ
弁護士は、いじめの再発防止に向けた取り組みを適切に行うよう、学校側に対して働きかけます。
たとえば、学校側にいじめに関する定期的な調査・アンケートの実施や安全配慮義務の存在を背景に具体的な対策(加害生徒への指導、被害生徒のクラスや席の変更など)を求めたり、学校に「いじめ対策委員会」の設置を促したりすることが考えられます。
子どもが安心して過ごせる環境を整えるためにも、再発防止への働きかけは弁護士を通じて行うことをおすすめします。 -
(3)損害賠償に関する加害者や学校との交渉の代理
いじめの被害者は、加害生徒や学校の設置者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
損害賠償請求をするためには、法的にいじめを立証し、被害の深刻さについて正当な評価を得ることが重要です。
弁護士は被害者の代理人として、いじめの事実や被害状況を精査し、医師の診断書などの証拠資料を整理した上で、加害生徒や学校の設置者に対して損害賠償請求を行います。法的根拠に基づいて損害賠償を請求することにより、適正額の示談金を得られる可能性が高まります。 -
(4)損害賠償請求訴訟の代理
加害生徒や学校の設置者との示談交渉がまとまらない場合は、裁判所に損害賠償請求訴訟を提起することも考えられます。
弁護士は被害者の代理人として、いじめに関する損害賠償請求訴訟の対応を全面的に代行します。複雑な訴訟手続きにも、弁護士ならスムーズかつ適切な対応が可能です。
訴訟の判決が確定すると、その内容が最終的な結論となるため、慎重な対応が求められます。訴訟を提起する際には、弁護士のサポートを受けながら十分な準備を整えましょう。 -
(5)刑事告訴のサポート
暴行・脅迫・強要など、加害生徒の行為が犯罪に当たる場合には、警察官に対して刑事告訴をすることも考えられます。刑事告訴を行えば、警察による捜査の結果、加害生徒の摘発につながる可能性があります。
弁護士は、刑事告訴のサポートも行います。告訴状の作成を代行することに加えて、警察署にも同行して警察官に事情を説明し、刑事告訴がスムーズに受理されるように尽力いたします。参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
5、まとめ
中学校に通う子どもがいじめに遭っていることが分かったら、子どもを救うため迅速に対応することが大切です。
いじめ被害を解決するためには、弁護士のサポートが役立ちます。弁護士は、いじめの状況や被害者の気持ちに寄り添いながら、適切なアプローチでいじめ被害の解決を目指します。
ベリーベスト法律事務所では、学校問題専門チームを組成しており、いじめ被害の解決に向けて真摯に取り組んでおります。中学校のいじめで、学校側と交渉したい、相手に損害賠償請求をしたい等お考えの場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
米澤 弘文
所属:東京弁護士会 登録番号:53503
学校問題専門チームのリーダーとして、いじめや退学、事故など、学校・保育園・幼稚園等の管理下で発生する問題に幅広く対応。
東京弁護士会「子どもの人権110番」では長年にわたり相談業務に従事しているほか、ラジオやWEBメディアを通じて学校トラブルに関する情報発信にも力を注ぐ。
- ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
いじめのコラム
-
更新日:2026年02月02日 公開日:2026年02月02日
- いじめ
 性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら
性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら -
更新日:2025年12月16日 公開日:2025年12月16日
- いじめ
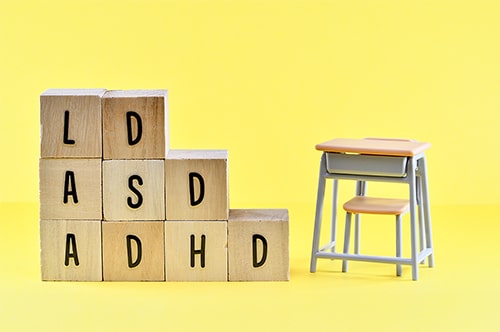 発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら
発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら -
更新日:2025年10月22日 公開日:2025年10月22日
- いじめ
 高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
通話