いじめが原因の自殺|学校側に求める調査と弁護士に相談するべき理由
- いじめ

令和6年における小中高生の自殺は529人と、過去最高の人数を記録しました。513人だった令和5年から16人増加し、統計が開始された1980年代以降、最も多い数となります。
いじめが原因で子どもが自殺してしまった場合、保護者の方の無念は計り知れません。少しでも子どもの思いに報いるため、学校側に対して適切な調査の実施を求めることが重要です。
本記事ではいじめを原因とする自殺について、学校側がとるべき対応や、被害者遺族が学校側に調査を求める際のポイントなどを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
出典:「令和6年中における自殺の状況」(厚生労働省自殺対策推進室・警察庁生活安全局生活安全企画課)
1、いじめが原因で児童生徒が自殺した場合に、学校側がとるべき対応
いじめを原因とする児童生徒の自殺は、いじめ防止対策推進法に定義される「重大事態」に当たります(同法第28条第1項)。
学校側は、重大事態に当たる自殺が発生したと認めた場合に、調査・報告・対処・再発防止措置などを行うことが義務付けられています(同法第28条~第32条)。
具体的には、学校側は以下の対応をとらなければなりません。
-
(1)教育委員会、行政機関などへの報告
児童生徒の自殺を含む重大事態につき、学校は上位の行政機関などへ報告を行わなければなりません。
重大事態の報告先 ① 国立大学の附属学校
国立大学法人の学長または理事長を通じて、文部科学大臣に報告(いじめ防止対策推進法第29条第1項)
② 地方公共団体が設置する学校(公立学校)
教育委員会を通じて、当該地方公共団体の長に報告(同法第30条第1項)
③ 公立大学の附属学校
公立大学法人の学長または理事長を通じて、地方公共団体の長に報告(同法第30条の2)
④ 学校法人が設置する学校(私立学校)
都道府県知事に報告(同法第31条第1項)
⑤ 学校設置会社が設置する学校(株式会社立学校)
学校設置会社の代表取締役または代表執行役を通じて、認定を受けた地方公共団体の長に報告(同法第32条第1項)
⑥ 学校設置非営利法人が設置する学校(NPO立学校)
学校設置非営利法人の代表理事を通じて、認定を受けた地方公共団体の長に報告(同法第32条第5項)。 -
(2)調査組織の設置、調査の実施
児童生徒の自殺を含む重大事態を把握した場合、学校の設置者および学校は、速やかに調査組織を設置し、事実関係を明らかにするための調査を行うことが義務付けられます(いじめ防止対策基本法第28条第1項)。
具体的な調査の方法については、後述します。 -
(3)遺族に対する調査結果の説明、報告
学校の設置者または学校が児童生徒の自殺について調査を行った場合、被害児童生徒の保護者に対して、事実関係などの必要な情報を適切に提供しなければなりません(いじめ防止対策基本法第28条第2項)。
具体的には、以下のような事項に関する情報提供が求められます。- いじめの時期
- いじめの加害者
- いじめの態様
- 学校側が講じた対応
-
(4)調査結果を踏まえた措置
児童生徒の自殺を含む重大事態の調査結果を踏まえて、学校の設置者および学校は、被害者のケア・加害者への対処・再発防止などの措置を講じる必要があります。
なお、上位の行政機関などが再調査を行ったときは、重大事態への対処および再発防止のために必要な措置を講ずる義務を負います(いじめ防止対策推進法第29条第3項、第30条第5項、第31条第3項、第32条第3項)。 -
(5)調査結果の公表検討
児童生徒の自殺を含む重大事態に関する調査結果は、特段、何かの支障がなければ公表することが求められます。
公表の有無は、学校の設置者および学校において、以下の事情を総合的に考慮して適切に判断します。- 事案の内容や重大性
- 被害児童生徒および保護者の意向
- 公表した場合の児童生徒への影響
2、いじめを原因とする自殺について、学校側が行うべき調査
学校現場における自殺に関する調査については、文部科学省が「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針」を公表しています。
参考:「子供の自殺が起きたときの背景調査の指針(改訂版)」(文部科学省)
同指針では、自殺に関して学校側が実施すべき背景調査を、「基本調査」と「詳細調査」の2つに分類しています。
-
(1)基本調査|指導記録等の確認・聴き取り調査など
基本調査は、自殺または自殺が疑われる死亡事案全件を対象として、事案発生後速やかに着手しなければなりません。
具体的には、以下のような調査を基本調査として行うことが求められます。① 遺族との関わり・関係機関との協力等
遺族の心情に配慮して、今後の接触を可能とするような関係性を構築します。
また、警察や亡くなった子どもと関わりのある行政機関・医療機関との情報共有を行います。
② 指導記録等の確認
指導記録、亡くなった子どもの作文・作品、連絡帳や生活ノート、教科書・メモ・プリント類などを集約して確認・保管します。
③ 全教職員からの聴き取り
原則として3日以内をめどに、できる限りすべての教職員から、亡くなった子どもに関して把握している情報を聴き取ります。
④ 亡くなった子どもと関係の深かった子どもからの聴き取り
学級や部活動などにおいて、亡くなった子どもとの関係が深かった子どもに対する聴き取り調査を行います。基本調査によって得られた情報は、重大事態に関する行政機関への報告や、遺族に対する説明などに活用されます。
-
(2)詳細調査|調査組織による専門的な調査
詳細調査は、基本調査を踏まえて必要な場合に、外部専門家を加えた調査組織が行う詳細な調査です。いじめとの因果関係が疑われる自殺については、調査委員会・第三者委員会などを組織して、詳細調査を実施することが求められます。
詳細調査は、その公平性・中立性を確保するため、弁護士・精神科医・学識経験者・心理や福祉の専門家などであって、事案関係者と直接の人間関係や特別の利害関係を持たない者を調査組織に参加させて行います。
詳細調査の具体的な内容としては、以下の例が挙げられます。- 学校以外の関係機関への聴き取り
- 子どもに対して自殺の事実を伝えたうえで実施するアンケート調査、聴き取り調査
- 遺族からの聴き取り
詳細調査の結果は、報告書にとりまとめて他校を含めた教職員へ共有するとともに、遺族に対してもその内容を説明することが求められます。
3、いじめを原因とする自殺の調査を学校側に求める際のポイント
いじめが原因で自殺した子どもの遺族が、学校側に調査を求める際には、いじめの証拠や学校側とのやり取りの記録を保存し、学校側に示すことが効果的です。
自殺の原因がいじめである可能性が高いと学校側が認識すれば、調査が実施される可能性が高まります。
しかし、さまざまな資料を提出して調査の開始を求めても、学校側が適切に動いてくれない・いじめを認めずに隠蔽(いんぺい)を図ろうとするケースもあり得ます。
そのような事態を防ぐためには、できる限り早期に弁護士へ相談することが有効な手段となります。弁護士が法的な根拠を示して調査を求めることで、学校側の対応を促すことができます。
4、学校で発生したいじめの法的責任|誰が責任を負うのか?
学校で発生したいじめについては、以下の者が法的責任を負う可能性があります。
-
(1)加害児童生徒・保護者
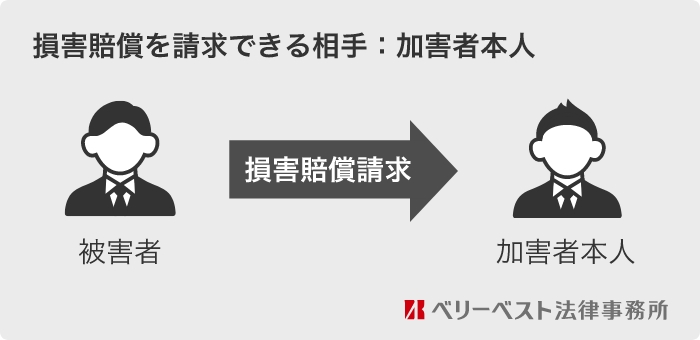
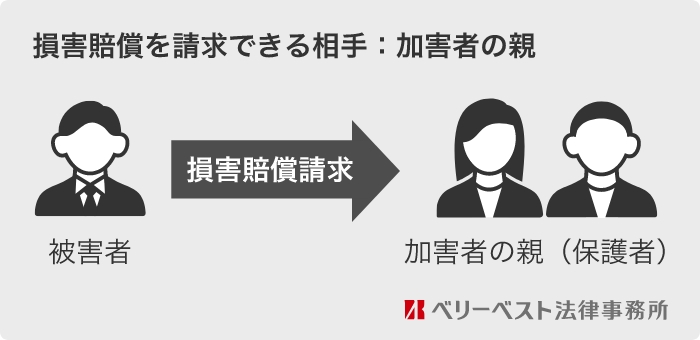
いじめによって被害者が受けた損害については、原則として加害児童生徒本人が不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法第709条)。
ただし、加害児童生徒が若年(おおむね10~12歳未満)で責任能力がない場合は、保護者が本人の代わりに監督義務者としての損害賠償責任を負います(民法第712条、第714条)。
また、いじめの過程で暴力が振るわれた場合には暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(刑法第204条)、金品を脅し取った場合には恐喝罪(刑法第249条)が成立するなど、加害児童生徒は犯罪の責任を問われる可能性もあります。
ただし、加害児童生徒が14歳未満の場合は犯罪の責任を問われず、家庭裁判所の保護処分が行われることがあるにとどまります(刑法第41条)。 -
(2)教職員|ただし国公立学校の場合は責任を負わない
教職員がいじめを漫然と放置した場合には、加害児童生徒(または保護者)に加えて、教職員もいじめの被害者に対して不法行為に基づく損害賠償責任を負います(民法第709条)。
ただし、国公立学校の教職員は、いじめの被害児童生徒に対する損害賠償責任を負わないと解されています(最高裁昭和30年4月19日判決)。 -
(3)学校の設置者
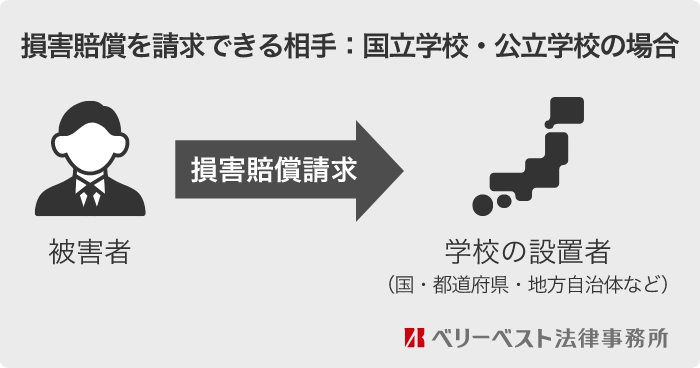
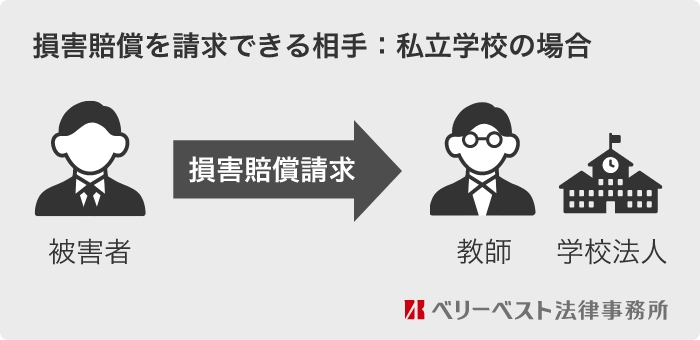
いじめの発生について教職員に故意または過失が認められる場合には、学校の設置者もいじめの被害者に対して損害を賠償しなければなりません。
国公立学校の場合は国家賠償責任(国家賠償法第1条第1項)、私立学校の場合は使用者責任(民法第715条第1項)がその根拠となります。
5、いじめを原因とする自殺について弁護士に相談すべき理由
いじめが原因で子どもが自殺してしまったら、できる限り早く弁護士へご相談ください。
弁護士は被害者遺族の代理人として、迅速かつ適切な調査および報告を行うよう学校側に対して働きかけます。また、加害児童生徒やその保護者、教職員、学校の設置者に対する損害賠償請求についても、弁護士にご依頼いただければ全面的に代行いたします。
弁護士は被害者遺族に寄り添いながら、法的根拠に基づいた主張や請求を行い、1日も早く事実関係を明らかにできるようサポートいたします。また損害賠償請求や刑事告訴などについても弁護士が代理人として対応いたします。弁護士への早めのご相談が解決に向けて重要となりますのでまずはご相談ください。
参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
6、まとめ
いじめが原因で自殺してしまった子どもの思いに報いるためには、学校側に徹底的な調査を求め、事実を明らかにしたうえで、加害児童生徒・保護者・学校などに損害賠償という形での責任追及が可能です。学校側に迅速かつ適切な調査を求める際には、弁護士による法的根拠に基づいた主張や請求が有効な手段のひとつです。
ベリーベスト法律事務所は、被害者遺族のご心情に寄り添いながらサポートいたしますので、お早めにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
米澤 弘文
所属:東京弁護士会 登録番号:53503
学校問題専門チームのリーダーとして、いじめや退学、事故など、学校・保育園・幼稚園等の管理下で発生する問題に幅広く対応。
東京弁護士会「子どもの人権110番」では長年にわたり相談業務に従事しているほか、ラジオやWEBメディアを通じて学校トラブルに関する情報発信にも力を注ぐ。
- ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
いじめのコラム
-
更新日:2026年02月02日 公開日:2026年02月02日
- いじめ
 性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら
性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら -
更新日:2025年12月16日 公開日:2025年12月16日
- いじめ
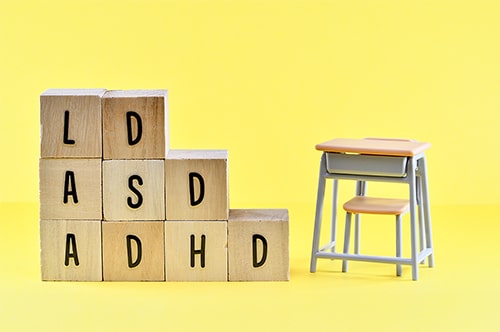 発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら
発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら -
更新日:2025年10月22日 公開日:2025年10月22日
- いじめ
 高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
通話