子がいじめられた時の対処法│学校との敵対を避け、法的措置も視野に
- いじめ

いじめは、子どもの心に大きな傷を残す出来事です。
いじめにより深く傷ついた子どもは、学校に通えなくなってしまったり、最悪のケースでは自ら命を絶ってしまったりすることもあります。子どもからのSOSに気付いた親としては、適切に対処することが求められますが、どのように対処すればよいか悩んでしまう方も少なくありません。
今回は、子どもがいじめられた時の適切な対処法や法的措置、学校への働きかけ方等についてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、いじめとは|どこからがいじめ?
いじめの定義については、時代とともに変遷してきましたが、現在は、いじめ防止対策推進法により、以下のように定義されています。
このように、いじめられている側が「心身の苦痛」を感じた場合、「いじめ」となりますので、子ども本人の気持ちがいじめの判断基準となる点がポイントです。また、近年は、SNS上などでいじめが行われることも増えてきていますが、いじめ防止対策推進法では、インターネットを通じて行われるものも含むと定義されています。
2、子どもがいじめられた時の対処法
子どもがいじめられた時は、どのように対処すればよいのでしょうか。以下では、子どもがいじめられた時に保護者がとれる対処法について説明します。
-
(1)子どもとの向き合い方に関する対処法
子どもがいじめられていることに気付いたときは、子どもに対して、以下のような対応をとることが望ましいといえます。
① 子どもの居場所を作る
いじめを受けている子どもは、学校に行くこと自体苦痛に感じていることも多く、学校に居場所がないことも考えられます。どこにも居場所がないと感じると、不安や絶望感から自ら命を絶ってしまうリスクなどが高くなってしまいます。
そのため、親としては、子どもが安心して過ごせる場所を家庭の中で作ってあげることが大切です。
② 親は味方であることを伝える
子どもにとって頼れるのは、もっとも身近にいる親です。子どもを責めたり、無理に学校に行かせようとしたりすると、子どもは、味方であるはずの親を信頼できなくなってしまいます。
子どもがいじめられていることに気付いたときは、子どもの気持ちに寄り添って、親は味方であるということを伝えるようにしましょう。
③ 子どもの意思を尊重する
子どもがいじめられていると親としては何とかしてあげたいと思い、さまざまな対応を考えるでしょう。しかし、たとえば子どもが転校したいという気持ちがあるにもかかわらず、無理に学校に通わせてしまえば子どもに大きなストレスが生じてしまいます。
そのためまずは、子どもの意見や考え方をじっくりと聞き取り、できる限り子どもの意思を尊重してあげることが大切です。 -
(2)いじめ問題の解決に向けた対処法
いじめ問題の解決に向けては具体的に以下のような対応を検討しましょう。
① 子どもの話を聞きながらいじめの内容などを整理・文章化する
子どもがいじめに関する話をしてくれるようであれば、子どもの話を聞きながらその内容を文書にまとめておくようにしましょう。学校でもいじめの聞き取りがなされることがありますが、いじめられた子どもは、教師や加害者の前では畏縮してしまい、本当のことを伝えられない場合も多くあります。
子どもが勇気をもって親にいじめを打ち明けてくれた時には、まずはじっくりと子どもの言葉に耳を傾けてあげるようにしてください。
そして、加害者からされて嫌だった行為や言われて嫌だった発言の具体的な内容と、それらの出来事が起きた日時などの情報を、可能な範囲で整理して文書として残しておきましょう。
② いじめの証拠を集める
いじめがあったかどうかについて学校や加害者側と争いになった場合には、いじめの証拠が重要となります。いじめられていた子どもの証言も証拠になりますが、それを裏付けるような客観的な証拠があればより確実にいじめを立証することができます。
いじめを立証するための証拠としては、以下のようなものが挙げられます。- いじめにより壊された物
- 教科書やノートへの落書き
- SNSなどで誹謗(ひぼう)中傷が書かれている画面のスクリーンショット
- 子どもが怪我をしたことがわかる診断書
- いじめられている状況を録音、録画したデータ
- 第三者からの証言
③ 学校に相談する
子どもの話を聞いたうえで、いじめを裏付ける証拠を集めて、まずは学校に相談しましょう。
子どもがいじめられている状況では、感情が抑えられず学校を責めたくなるかもしれません。しかし、感情的な対応では学校側はクレーマーなどとして捉えてしまい、真剣にいじめ問題の解決に取り組んでくれないおそれもあります。そのため、できる限り冷静に話し合いを進めることが大切です。
④ 学校に調査を求める
学校にいじめに関する通報があった場合には、学校には調査する義務が生じます(いじめ防止対策推進法23条2項)。また、いじめ重大事態(いじめ防止対策推進法28条1項)にあたる場合には、第三者委員会を設置して調査を進めなければならないとされています。
このような根拠をもとに、学校に対してまずは調査を求め、いじめの事実を把握してもらうことも有用です。
⑤ 法的措置の検討
いじめによる被害を受けた場合には、学校および加害者に対する法的措置も検討できます。具体的には、子どもが受けた精神的苦痛に対しては、損害賠償請求という形で慰謝料の支払いを求め、加害者から暴行・脅迫・恐喝などの被害を受けた場合には、刑事告訴をすることにより加害者の刑事責任を問うことなどが可能です。
⑥ 弁護士に相談する
いじめ問題を解決したいが、どのように対応すればよいかわからないという方も少なくありません。また学校にいじめの相談をしても適切に対応してもらえないというケースもあり得るでしょう。そのような場合、弁護士に相談することで法的な観点で解決策のアドバイスをもらえたり、弁護士が代理人として対応することで学校側が対応を進めてくれたりすることがあります。
いじめ問題に精通した弁護士であれば、具体的な状況に応じて、最善の行動をアドバイス・サポートすることができますので、弁護士は有効な相談先のひとつといえます。
参考
3、いじめの解決に向けて対処を進める際のポイント
いじめ問題の解決に向けて対処を進める際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
-
(1)学校に相談するときは書面を提出する
いじめ問題の解決に向けた対応を学校に求める際には、口頭での申し出ではなく、必ず書面で行うようにしましょう。口頭での申し出では、後日、言った言わないのトラブルになる可能性や、担任で話が止まってしまい対応が進まない可能性があります。
学校宛てに書面を送付することで、学校全体で問題を共有することができますので、より適切な解決に向けた取り組みが期待できるでしょう。 -
(2)学校と敵対関係にならないようにする
いじめ問題は、学校と協力して対応していかなければならない問題です。親としては、いじめに気付かず放置した学校は、いじめの加害者と同様に子どもの「敵」であると考えてしまいます。しかし、学校側を敵対視して、高圧的な態度で交渉してしまうと、その後の交渉が難航するおそれがあります。
学校との関係が悪化するのは、いじめ問題の解決だけでなく、子どもの学校生活にも悪影響を及ぼすおそれがありますので、学校とは必要以上に敵対関係にならないように話し合いを進めていかなければなりません。
4、子どものいじめ問題において弁護士ができること
いじめ問題の相談は、学校だけでなく弁護士も有効な相談先です。子どものいじめ問題でお困りの方は、弁護士に相談することをおすすめします。
-
(1)証拠集めのアドバイスができる
いじめの有無に関して争いがある場合には、いじめられていたという証拠が非常に重要になります。どのような証拠が必要になるのかについては、具体的な状況によって異なりますので、まずは弁護士に相談して、証拠集めのアドバイスをしてもらうとよいでしょう。
-
(2)代理人として学校と交渉できる
親と学校側の話し合いではどうしても感情的になってしまい、学校との間で敵対関係が生じる可能性があります。弁護士であれば、法的観点から冷静に話し合いを進めることができますので、いじめ問題をよりスムーズに解決に導くことが可能です。また、学校との話し合いは負担も大きいですが、弁護士に任せればそのような負担はほとんどありません。
-
(3)調査の働きかけや再発防止策の協議ができる
学校側がいじめを認識していない場合には、いじめの調査を実施する必要があります。被害者の親からの申し出だけでは、学校側が動いてくれない場合でも、弁護士から働きかけをすることで学校側が応じてくれる可能性が高くなります。
また、弁護士は今後の再発防止に向けた協議においても具体的な提言を行うことができますので、子どもが安心して生活できる学校環境を整備することが可能です。 -
(4)法的措置をとる場合の手続きなどを対応できる
学校側との話し合いで解決できなかった場合などには、損害賠償請求または刑事告訴などの法的措置を検討するケースもあります。
法的措置となれば法律の知識や経験が必要になりますが、弁護士に任せることで、これらの手続きも適切に進めてもらうことができます。ひとりで対応が難しいと感じる場合には、弁護士が寄り添ってサポートしますので、まずは弁護士にご相談ください。
参考
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
5、まとめ
子どもがいじめられていると気付いたときは、まずは子どもに寄り添って子どもの心のケアをしてあげることが大切です。そして、いじめ問題の解決に向けて行動する際には、弁護士のサポートを受けながら最適な方法を検討していくようにしましょう。
いじめ問題では学校以外に弁護士も有効な相談先です。子どもがいじめられてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。

ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
米澤 弘文
所属:東京弁護士会 登録番号:53503
学校問題専門チームのリーダーとして、いじめや退学、事故など、学校・保育園・幼稚園等の管理下で発生する問題に幅広く対応。
東京弁護士会「子どもの人権110番」では長年にわたり相談業務に従事しているほか、ラジオやWEBメディアを通じて学校トラブルに関する情報発信にも力を注ぐ。
- ※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています。
いじめのコラム
-
更新日:2026年02月02日 公開日:2026年02月02日
- いじめ
 性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら
性的いじめとは? 見えにくい子どもの性暴力被害と保護者ができること性的いじめは子ども同士であっても立派な「性暴力」であり、深刻な権利侵害にあたります。無断で身体を触られる、性的な言葉を投げかけられる、着替えやトイレをのぞかれ…コラム全文はこちら -
更新日:2025年12月16日 公開日:2025年12月16日
- いじめ
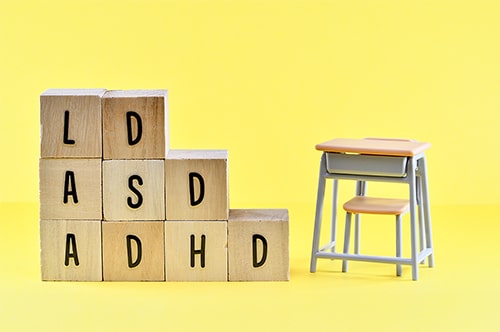 発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら
発達障害の子どもがいじめられたら? 保護者ができること【対策と相談先】発達障害のある子どもは、特性により友人関係で誤解を受けたり、トラブルに巻き込まれたりすることがあります。文部科学省の調査では、発達障害が疑われる児童生徒は増加…コラム全文はこちら -
更新日:2025年10月22日 公開日:2025年10月22日
- いじめ
 高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
高校生のいじめ│見えない「ネットいじめ」等に保護者はどう対応?高校生のいじめは、冷やかしやからかい、悪口や脅し文句などの言葉によるいじめが依然として多い一方で、仲間外れやSNSでの誹謗中傷といった「目に見えにくい心理的な…コラム全文はこちら
学校での問題・トラブルの
法律相談予約はこちら

通話
通話